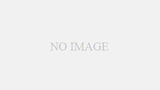(つづき)
この無名が、何々という名前をつけてきますと、これは無名ではなく、神そのものではなく、神の現われとしての存在となってくるのです。そして、霊的な微妙な波動としての存在から、次第に粗い波動の存在、つまり、物質的な現われに変化してくるのであります。
ですから、名がつくと、つまり有名になってまいりますと、それは万物を生みなしたことになり、万物の母なりということになるのであります。
ここに一つずつの布巾と雑巾があるとします。この布巾と雑巾とは、その名がついたときに、その役目が定まってしまっているのです。一反の木綿の布地が、その布地としては、布巾に使われるか、雑巾に使われるか定まっていませんが、いざ人間の側で、これは布巾に、これは雑巾にと定めてしまうと、その反物は、その定められた名の通りになってしまうのです。
すべてそうしたもので、名がつけば、その名に縛られてしまうのですが、人間はその名をさかのぼって、神のみ心そのものの中に入りきって、神即ち無名と一つの働きに合体することが出来るものなのです。
(中略)
『故に常無以(じょうむもっ)てその妙を観んと欲し、常有以てその徼(きょう)を観んと欲す。この両者は、同出にして名を異(こと)にす。同じく之を玄(げん)と謂(い)う。玄の又玄は、衆妙の門なり。』
常無というのは、無名即ち神そのもののことであります。
その神そのものの中に、妙々不可思議なる絶対力というか、大智慧というか、大能力というか、そうした、妙なる実在の姿を観ることが出来るのであり、現われとしての天地の中に、徼(きょう、とりで)つまり差別の姿を観ることが出来るのであります。
しかしこの両者は、まったく一つの実在の姿であり、現われの姿であって、名を異にしているだけである、と云うのであります。
(つづく)
五井昌久著『老子講義』より