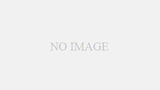(前略)次に進み出たのは、四十がらみの体のがっちりした男であった。
「わっしは家を作る職人でございます。どうも生来気が短すぎまして、先日も友だちとやり合いまして、そいつに大怪我をさせてしまいました。原因は大したことじゃあないんですが、ついかっとしますと、すぐ手が動いちまうんです。このため、いつでも年とったお袋さんに心配をかけ通しで、こんなことじゃあとても、死んでからろくなところへゆかれっこねえと思いますんで、どうか尊者様のお力で、この悪い気性を叩きなおしていただきたいんでございます」
と、真実を面に現わしていった。目連尊者はにこにこ笑いながらこの男の言葉を聞いていたが、
「そなたが自分の欠点に気づいて精舎にまいったことで、その欠点の大半は癒(なお)ったも同然である。自分の欠点に気づいたことが第一、それを癒そうと努力することが第二、第三に自分では癒らぬことに気がついて、仏のみ下に自己の欠点をさらけ出して裸になったこと、これで、そなたの欠点は癒ったも同然なのである。今日限り、もはやそなたの短気という欠点は消えうせてしまったのだ。わかったかね。今日限り、この場限り、そなたの欠点は仏様の中に吸い込まれてしまって、もうそなたの心の中には短気という思いはなくなってしまっているのだ」「お言葉ですが、わっしの生まれながらみたいなこの短気が、もうなくなっちまったんですかね」
と、目連の話が一息ついた時に、この男は不審そうにこう訊きかえした。「そうじゃよ。もう無くなってしまったのだ。あると思うなら今ここで腹を立ててみなされ」
「へ、へ、へ、どうも、そう早急に腹は立ちませんやね。それに、なんにも腹を立てる原因もありませんしねえ……・」
「そうかの。すると今は腹の立たないそなたがいるわけだのう。いつものそなたはどちらのそなただ?」
「へえ、そうですね。今こうしているようなわっしでございますが」
「そうであろう。今のそなた、腹の立たないそなたが真実のそなたであろう。短気というそなたは、なんらかの原因によって、外へ引っ張り出されるそなたの欠点と思っている感情であろう。だから、そなたの真実の心、つまり本心は、いつも平然としているのだ。怒って外へ飛び出してゆくのは、そなたの本心の周囲についている塵(ちり)ほこりであって、外へ飛び出してゆけば、それだけ消え失せて無くなってゆくわけになるのだ。わかるだろうな、この理(ことわり)が?」
「……・」(つづく)
五井昌久著『小説 阿難』より