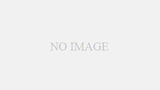先日知人が、高島屋で催された良寛展から、良寛の書の写真版を買ってきてくれた。私は少年の昔は、良寛さんの人格が好きで、良寛さんのことを書いてある本をあさり読みしては、こんな純真な、こんな柔和な、こんな円満な人格に自分もなりたいものだ、なんとかして良寛さんになりたい、良寛さんこそ自分の道を指し示す唯一無二の人である、と自分の性情に照らし合わせて、良寛さんを慕いつづけていたのであった。(中略)
その良寛さんを、今日大人になった私が書の上からじっくりと見つめて、今更のように良寛さんの童心、その純粋無礙(むげ)なる心に驚いてしまったのである。四十点ばかりあるその書は、時代によっては著しい変化のあるものがあるが、その書はいずれもなんの把(とら)われもない、自由で大らかな筆の動きが見え、この人の人格に、じかに接している気持になってしまう。中には非常に書境の高い、誰が見ても、文字として秀れた立派な遺墨もかなりあったが、私が一番感動したのは、その表紙になっていた「天上大風」という文字であった。
その文字は、低学年の少年が書いたような文字であって、良寛の書であることを知らぬ人が見たら、恐らくは子供の書いた文字と思い違えてしまう程に、飾り気のない文字である。天という字の、上の横棒と下の一の間とが馬鹿に間があいていたり、人という字が、いかにも無造作のように、しまいがかすれて書かれていたりしているのだ。だが心してみると、なんという欲のない、何という飾り気のない、なんという純心で把われのない、なんという自由な、なんという清々しい一筆一筆であろうか、とその一字一字から眼が離せなくなってしまうのである。良寛さんの純心無礙なる人格が、そのまま文字になって浮き出しているのである。良寛さんの日頃からの心境が、筆にも墨にもわずらわされず、そのままそこに画かれているのである。
私は自分の心が洗われるような気持になって、じっとその文字をみつづけ、閑があるとまた出してはじっとみつめていたのであった。私はこれだけ自己の心を、なんの隠しもなく裸で人に見せて、人に恥じないでいられる人を、あまり見たことがない。長年にわたり、様々な学問知識を身心につけ、様々な体験を経ていながら、童心をそのまま損なわずに一生終わっていった良寛さんのような人は、確かにいつの世においても、一服の清涼剤たるを失わない。偉大なる童心、純心無礙の人格、良寛和尚のような人が、今日にも何人か現われていたら、この世はそれだけで、清々しいのではないか、としみじみ思ったのである。(後略)
五井昌久著『神への郷愁』より