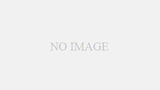(つづき)釈尊はそこで一息つかれて、聴衆を見廻された。その時、聴衆の中央に熱心に耳傾けていた一人の長者が、「世尊(せそん)、私共愚かなる者は、常に因縁性の肉体想念で、もろもろの事柄を思考し、修行致そうと思い勝ちなのであります。自己のうちなる如来性(にょらいしょう)を輝かすということが、真に難しく、うちなる如来(にょらい)と想えば、その思いに把われて、一点に想いが凝(こ)り固まり、それがかえって、わが心の自由を奪ってしまうのであります。このような時、私はうちなる如来というより、ただひたすら世尊のご尊像を想い浮かべて、それによって自由心を得、碍(さわ)りなき心、と成ります方が、容易なような気が致しますが、この点を、世尊にお教え頂き度(た)く存じます」と、恐る恐る質問して、叩頭した。
「うちなる如来というも、形あるものではない。如来とは、来たって来ることなく、去って去ることなく、拡がれば、宇宙無限大となり、握れば、無現小の微粒となり空(くう)となる。うちにあると思えばうちに把われ、外にあると思えば外に把わるる心は、如来を知る心ではなく、そなたの申す如く、因縁性(肉体想念)の心である。因縁性の心をもってしては、何処に如来を求めようとも、求め得ることは出来ない。
そなたが、我(われ)を想う時にこそ自由を得るという理(ことわり)は、我が肉体を縁として放つ如来の光明が、そなたの因縁性を一度(た)び消滅せしめることによって、その時、そなたの心が如来と相通ずるからである。我を想えば、我はそなたの心の中にあって、そなたの如来心を輝かせるものである。我(われ)とそなたとは如来心において一つのものであることを知るならば、何処(いずこ)にあって、そのような状態にあっても、自(おの)ずから如来心を輝かせることが出来るのである。すべてに解脱せる者を仏という。我(われ)はすべてを解脱せるものであるから、我(われ)を真実に想う時、そのものは解脱することが出来るのである。」(おわり)
五井昌久著『小説 阿難』より