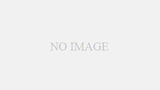釈尊は穏やかな言葉で法話をつづけておられた。聴衆は、菩薩摩訶薩(ぼさつまかさつ)を始め、大比丘(だいびく)、長者居士等々、道場一杯に謹聴していた。
「一切の衆生(しゅうじょう)は無始(むし)よりこの方、種々に鬘囀(てんとう)して、自己の想念というものを認め、肉体の自己を自己そのもの、自己の本体を誤認し、色(しき)、声(しょう)、香(こう)、味(み)、触(しょく)の迷いによって起る影を自心の相(すがた)としている。
人間の肉眼に見、肉耳に聞き、肉の鼻にかぎ、肉の舌に味わい、肉体に触るるすべてのものは、これみな迷いの縁にふれて現わるる影に過ぎないのである。
その影を実在と観ていることによって、如来(本心本体)の姿はうち深く隠れてその者たちには観ることも、把握することも出来なくなってしまったのである。
それは恰(あたか)も、眼を患っている者が、空中に華の咲いている様(さま)を観たり、月の姿を二つと見、三つとも見ているようなものであって、視覚の確(たし)かなる者からみれば、空中に華(はな)はなく、月の姿は一つより見えないのである。これは眼病によるその者の妄見(もうけん)であり、誤った見方である。
人々はそのような者を病者と呼びながら、自己そのものも、その病者と等しき妄念によって、実在するものをなしと観(み)、影として写っているものを実在として観ている。この念(おもい)を無明(むみょう)というのである。
この無明は、実態あるものではなく、夢中の人が、夢を見ているうちは、その夢の事物を無(む)なるものと思わずに過ごせど、一たび醒めるに及んでは、その事物は、実在せるものにあらず、実体なきものであることを知るが如きものである。
この肉体の生死の如きも、輪廻(りんね)する想念の如きも、すべて無明の産むところであって、人間の本来性には、生死も、輪廻もないのである。
生死を有りと観、輪廻を有ると観ることは、肉体そのものを本体と観、想念を我れの本心と想う誤りによるのであって、この理(ことわり)を知り得ぬ限りは、人間界の生老病死の苦しみから抜け出ることは出来ない。
肉体といい、想念といい、それらは実在にあらず、本体にあらず、如来性にあらざるが故に、ある因縁をはたせば、一瞬にして消え去りゆくものである。それらが有るということは、ただ単に無明によって生じたる因縁因果の流れとして存在せる如く観ゆるのである。
無明とは、如来心の明らかに顕われざるところにつけたる名称であって、如来のみ心顕わるれば、その光明によって、無明は忽(たちま)ちにして消ゆるべきものである。如来蔵の中には、起滅もなく、知見もない。従って迷うこともなく、覚(さと)ることもない。」(つづく)
五井昌久著『小説 阿難』より