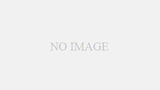(つづき)「また話を前に戻すが、そなたが、これではいけない、と思ったことによって、飛び出した塵ほこりはそのまま消え去って、再びそなたに中に返って来ることはない。
それは何故かというと、いけない、と思ったことは、短気というその感情を否定したことになる。もう再びその感情を自分の心の中に入れまいと絶(た)ったことになる。
本心と短気という感情との間の戸をしめてしまったことになるのだ。そうして置いたのだが、自分では、そういう結果になったことがわからずにいて、また別な塵ほこりが、怒りの感情になって、外に引き出されると、前の短気がまた自分に返って来たと思って、自分は短気で駄目だ、と今度は自分の本心まで否定してしまおうとする。
ところが本心は、そなたが肉体身として生まれて来ぬ前から存在するみ仏の心なのだから、いくら否定しても消えはしないで、そうした理由のわかる人のところへ、そなたを送りよこして来た。それが、今そなたがわしのところへ来て、わしにこうして相談している形になっているのだ。
ところがわしはみ仏の弟子で、み仏の心をよく知っており、そなたの本心もよく知っているので、わしが、そなたの本心と塵ほこりである短気という感情との間の境の戸になってあげることにした。だから今日限り、短気というそなたは存在しなくなってしまったことになる。わかるかね、このことが。
もしまた、そなたを怒らせるような原因が起こったら、目連さん目連さんとわしの名を呼ぶか、本心さん本心さんと自分の本心を呼び出すかするとよい。
もう短気という感情はそなたから無くなってしまってはいるのだが、それまで長年やっていた癖がまだいくらか残っているかも知れない。時によるとその癖が、ちょくちょく顔を出すかもしれないが、それはもう些細なもので、わしの名でも、そなたの本心でも、み仏の名でもよいから、しきりに心の中で呼んでいると、自然と消え去ってしまう。
それで外へ飛び出したら飛び出させておけ、たいした争いになるようなことはない。そんな感情は自然とみんな消え去っていって、やがてはそなたの本心だけが外まで輝き出すようになる。
短気ばかりじゃあない。すべて、そなたがいけないと自分の心で思うことは、みんなそうして消え去ってゆくのだ。
さあ、家へ帰ったら、早速、自分の本心さんを胸の中に呼んで、本心さん本心さん、間違った想いはみんな消して下さい、と呼ぶことにしなさい。
本心さんは、み仏と同じものなのだから、尊く明るく清らかで、輝きわたっているものなのだ。そなたは昨日までのそなたではなく、み仏の中に存在することを認識したそなたであることを忘れるではないぞ。
短気なぞは、吹けば飛ぶような、消えるに決まっている塵あくたなのだ」
目連尊者はわかりやすいように、親切に説き聞かせていた。聴いていた男は、いつか涙ぐんでしまったが、やがて世にも嬉しそうに両目を輝かせて、
「尊者様、わっしは自分が馬鹿なつまらない男だと、今の今まで思っておりましたが、只今のお話で、つまらない馬鹿で短気なわっしというものは、実は、塵やほこりの方だっていうことをわからせて頂きました。わっしの本心は、仏様と同じだ、とお聞きしちゃあ、その本心を外に出して、本心そのままの働きをしなけりゃあ、自分自身に申し訳ないような気がしてまいりました。本当に本当に良くわかりましてございます。尊者様、本心様、ありがとうございます。ありがとうございます。」
男は、嬉し泣きにむせびながら、輝くようにその場をさがっていった。目連尊者は、次から次へと明快に答を与えて、人々の心に仏子としての灯を点(とも)してやっていった。(おわり)
五井昌久著『小説 阿難』より