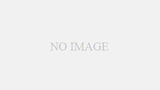少年は空を愛していた
手もとどかぬ
無限の高さ
無限の広さ
その空の中に
少年の心はいつも住んでゐた
その青の色は少年の笑顔であり
その灰色は少年の泣き顔である
そして太陽は少年の父であり
月は少年の太陽であつた
建ち並ぶ長屋の路地裏から
夕暮はサンマを焼く臭ひがする
地上の父は勤めから帰へり
地上の母はカマドに火をたく
少年はその路地に立って
屋根と屋根の間から
倦(あ)かずに空をみつめてゐた
夕べの空にくりひろげられてゆく
星の物語り
少年はその星たちの物語を聞いてゐた
少年の魂にその星の一つがさゝやきかける
君が此(こ)の世界にゐた時にね
─少年の中に次第に魂の昔が甦(よみがえ)つてきた
あゝあの一番光る星の中に私が生きてゐた事があつたつけ─
あの偉大な歴史の聖者たちと
共に働いてゐた事があつたのを
少年の魂ははじめてはつきり識つたのだが
地上の母の呼び声に一瞬
少年の魂は地界に還へり
多くの年月が過去として流れ去つてゆく間中
其の時の記憶は魂の外に表はれ出なかつた
少年は青年となり
壮年となつてゆき
地上界の様々な体験の中で
三界と云ふものを認識し
それを超える事に精進した
地上の父母も兄弟も
すべての地上界の俗縁は
もはや彼の因縁生の波状である事も
識つた或る夜の深い瞑想時
少年の日の魂の記憶を縁として
彼は一躍天界に昇(のぼ)つた
真我と個我の一体化
─光明遍照こうみょうへんしょう)─
遂ひに天地は彼の心の中で合体した
五井昌久著『ひゞき』より