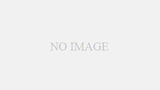(前略)
人間世界におけるすべての不安の根柢は死の恐怖にある。いかなる種類の苦しみに直面したとしても、死への恐怖を超越した人にとって、その苦しみは心の痛みにはならない。
死ほど、人間の関心をそそる出来事は他にあるまい。死は人間にとっての終りなのか、転移なのか、この謎が解けることによって、人間の進歩は一段と早まるに違いあるまい。
人間は肉体消滅によって失くなってしまうものではない。(中略)死とは幽界(以後は霊界をも含めて)への転出なのである。
肉体の死とは、幽界への誕生なのである。死ぬことを往生といったのは、このことを昔の人は知っていたからなのである。
肉体が死ぬということは、その中の神につながる分霊が(後にはただ霊という)幽体をつけたまま、肉体を抜け出た後の状態をいうのである。(中略)
人間とは肉体ではなく、霊そのものをいうのである。肉体とは霊の容れ物であって、霊の心のままに行動するものなので、ちょうど自動車が運転手によって走っているように、霊の運転によって種々の行動を為すのが肉体なのである。(中略)
直霊(神)から分かれた分霊がまず幽体を創り、その幽体を下着やシャツのように着け、その下に下着を着けた上に肉体をいう上着を着けた姿を、普通は人間と呼んでいたので、その肉体の消滅を、人間の消滅と残された肉体界の人々は思い込んでしまっていたのである。
これを物理学的にいうと、霊体は非常に細かい周波数をもつ波長の体であり、肉体は粗い周波数をもつ波長の体であり、幽体はその中間の周波数をもつ波長の体であるということになり、分霊はその三つの体を自己の体としているのであるが、肉体に入るには必ず幽体をつけてゆかねばならぬのである。
それは霊体から肉体へ移るには、波長の周波数があまりにも違い過ぎて合わぬからである。
幽体は霊と肉体を結ぶ役目をもっているのであり、霊の念と肉体人間としての脳髄の想いとを、その体に録音しておく役目をもつのである。(この場合、幽体を念体ともいう)肉体人間の死によって、人間(霊)は幽体をつけたまま幽界において生活する。
この幽界にも肉体界(現界)と等しく、種々な生活があり段階がある。その生活は、幽体に蓄積されている想念の通りに実現されてゆく。この人の想念が憎しみに充ちていれば、憎しみに取りまかれた生活をする。愛深き想念ならば、愛深き想念の人々とともなる生活をする、というようになるのである。(つづく)
五井昌久著『神と人間』より