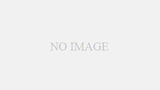(つづき)少年店員として日本橋の呉服屋に住み込みで働き、一九歳で独立し、五井商店を開いた。といって一軒の店を構えたわけではなく、自転車を使っての行商というか、外交を主にした商売だった。
いささかの不安はあれど独立す心さながら火の如く燃ゆ
売り売れぬ我が業ひを気にかくる母と夕餉を黙しつつ食す
独立した当時の短歌である。
意気に燃えておられたが商売人にはなりきれなかった。しかし心の中で、いつも「今に見ていろ」「このままでは終らない」という気持ちを持ち続けていた。商人になるのが最終目的ではなく、文学や音楽で世に立ちたい、という想いをひそかに燃やしていた。短歌ばかりでなく、声楽も専門的に学校に通って学んだ。
金儲け、というのは苦手だったようで、食べて勉強できるだけのお金が入れば、それで満足だった。終戦になり、やがて宗教心に心が向き、求められて掌療法で病気治しに歩かれた折も出されたお金は絶対に受け取らなかった。極端に恥ずかしがられたのだと思う。
そうした先生も、四〇代半ばを過ぎてから、恥ずかしい、という気持ちもなくなり、自然にお金を受け取れるようになったのだ、と述懐されている。
その頃のエピソードにこんなことがある。ある青年がはじめて月給をもらった。
「先生、これは私の感謝の気持ちです。どうぞ受け取ってください 」
と千円を包んで、先生に恥ずかしそうに差し出した。今の千円とちがって、昭和三三年(一九五八年)頃の千円である。青年としては就職先を世話していただいた、という感謝の気持ちの表れだった。
「とんでもない。君からもらうなんて」
「いえ先生、どうぞ受け取ってください。それでないと私の心が済みませんから」
青年は赤くした顔を、今にも泣き出しそうにしながら、逃げるようにお浄めの部屋から出てゆく。その後を先生があわてて追いかけ、
「じゃこうしよう。これはありがたくいただくよ。そしてあらためてこれを君の就職祝いに差し上げよう。ね、いいだろう」
いそいで青年の上着のポケットにお金包みを押し込まれた。
「よかった、よかった」とおっしゃりながら、青年と同じように顔を赤らめて、先生はそんなに暑くもないのに、パタパタと団扇をあおがれていた。
四〇過ぎから、先生も貯金を始められたようだ。会員から寄付を募らなくても、道場用地の購入が出来るよう、建物の建てられるよう、という外に、先生のまわりに、私のように何もかもご面倒をかける者が出はじめたからである。
会がどうなっても、つまり何かの加減で潰れても、解散してしまっても、まわりの者の生活の面倒ぐらいは見てやろう、と思ったからだと、先生はおっしゃっていた。
五〇歳を過ぎて、五井先生はおっしゃった。
「高橋くん、安心しな、会がどんなになっても、君たち家族が食いっぱぐれることがないくらい、お金が貯まったから」
億というぐらい貯まったのかと思ったら、その半分もなかったことが、先生の口からもれた。けれど私はありがたくありがたく、頭を垂れてその言葉をお聞きした。これには奥さまのお心もあったと承っている。(後略)
高橋英雄著『五井せんせい: わが師と歩み来たりし道』より